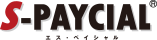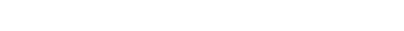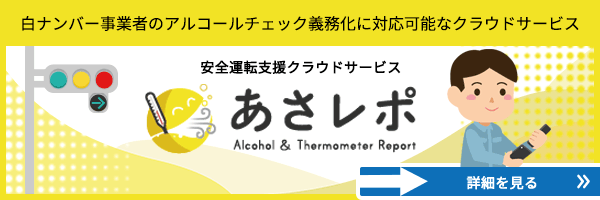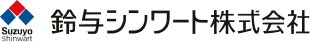年末調整電子化の義務?対象企業・メリット・電子化のポイントを解説!
目次
年末調整手続きの電子化は、一部の企業で義務化されています。
本コラムでは、紙による年末調整申告と電子年末調整申告の比較、義務化の対象企業・義務化の時期・電子化のメリットや電子年末調整サービスを導入する際の注意点などを解説します。
年末調整電子化(の義務化)とは?
まず、年末調整電子化とはどのようなものか、税制改正や義務化された項目について具体的に紹介します。
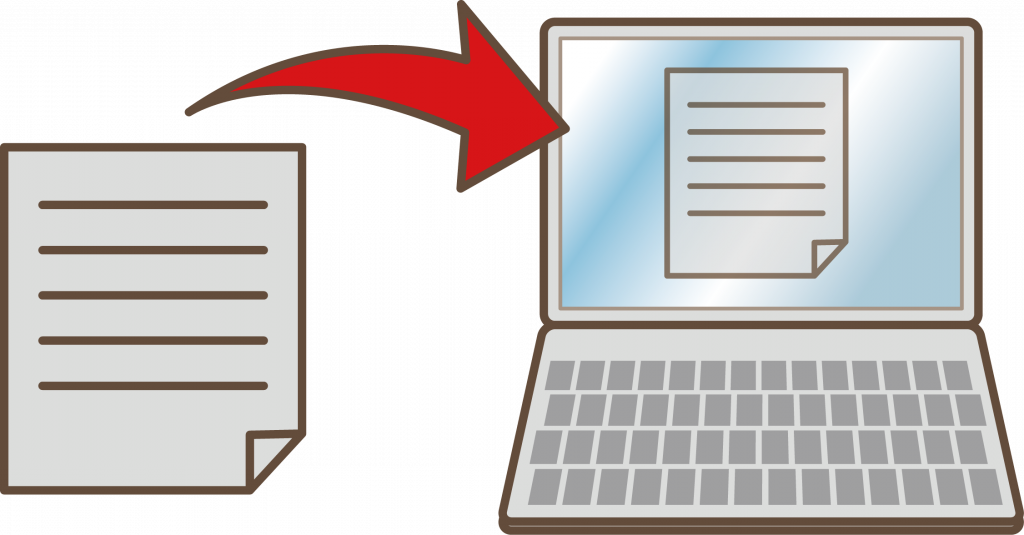
年末調整の電子化とは、年末調整に関わる申告書や控除証明書などをデータで作成、授受、保存することで事務担当者、従業員双方の負担を軽減する取り組みを指します。
従来の年末調整は、従業員に複数枚の紙を配布し手書きで手続きする方法が主流でしたが、平成30年度の税制改正により令和2年度分の年末調整から、ほとんどの書類が電子データで手続きすることが可能になりました。
これにより、記入や計算の手間が軽減され年末調整手続きが大幅に効率化されました。
<具体的な電子化可能書類一覧>
| 年末調整申告書の種類 | 申告書の電子化 | 控除証明書等の電子化 |
|---|---|---|
| 扶養控除等申告書 | 〇 | (控除証明書等なし) |
| 配偶者控除等申告書 | 〇 | 同上 |
| 基礎控除申告書 | 〇 | 同上 |
| 所得金額調整控除申告書 | 〇 | 同上 |
| 保険料控除申告書 | 〇 | 〇 |
| 住宅ローン控除申告書 | 〇 | 〇 |
引用:国税庁 PDF「年末調整手続きの電子化及び年調ソフトに関するFAQ」
例えば、ハガキなどで各自が保管していた保険料の控除証明書は、保険会社から電子データを取得して提出することが可能になりました。ただし、前提として勤務先が電子申告に対応している必要があります。また、控除証明書の原本が必要な場合もあるので、控除証明書の提出は勤務先の年末調整手続きのルールに則って進めていく必要があります。
<法令上、データ提出ができないため書面で提出又は提示する必要がある書類例>
国外居住親族に係る親族関係書類・送金関係書類、勤労学生に該当する旨の証明書等
引用:国税庁「年末調整手続の電子化に向けた取り組みについて」
どこからが「義務」?対象企業・時期・提出方法・罰則などについて
令和3年1月の申告分から、一部の企業では法定調書の電子化が義務化となりました。以下の条件に当てはまる企業は電子化で手続きする必要があります。この基準に違反した場合、罰則が課される可能性があります。
<義務化の対象企業>
前々年度(2年前)に発行した法定調書が種類ごとにみて100枚以上である企業
<義務化の概要>
2021年1月1日以降、法定調書は電子化し、インターネットを利用したe-Tax・光ディスク(CD/DVD)等・(国税庁長官の認定を受けた)クラウドサービス等を使用して提出しなければならない
引用:国税庁「法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax、光ディスク等又はクラウド等による提出義務」
これに該当しない企業は電子化の義務はなく、従来通り紙媒体での手続きも可能です。
<令和9年から年末調整義務化対象企業の範囲が拡大>
令和9年1月以降は、電子化が義務となる基準年の法定調書提出枚数が「100枚以上」から「30枚以上」に引き下げられます。令和7年(2025年)中に提出する法定調書の発行枚数が判定に影響します。
昨年まで義務化の対象外だった企業も義務化の対象となる可能性が出てきます。詳しい情報は、国税庁や専門サイトのガイドラインを参考にしてください。
参照:国税庁「e-Tax等による法定調書の提出が義務化されています!」
紙による年末調整申告と電子年末調整申告の比較

紙申告と電子申告とではどのような違いがあるのでしょうか?
主な違いは、電子申告により書類の配布や回収、確認作業が不要となり、作業時間が大幅に削減されることです。
年末調整申告を電子化すると昨年申告したデータの引き継ぎや、自動計算が導入されるため、ミスが減り、従業員・企業とも作業負担が軽減されます。また、印刷や保管のコストも削減できるため、環境に優しい運用が可能となります。
年末調整手続きの電子化 ~紙運用との比較~
| 紙での運用 | 電子化後の運用 「S-PAYCIAL with 電子年調申告」の場合 | |
|---|---|---|
| 事前準備 | 封筒、申告書、説明資料印刷など | 不要 |
| 発送作業 | 封入、投函 | 不要 |
| 未提出者管理 | 提出期限が過ぎてから直接や電話、メール等で督促 | リアルタイムで進捗確認 未提出者にメールで一斉督促 |
| 不備確認 | 金額誤りを再計算で確認 必須項目の記入不備確認 読みづらい文字の解読 証明書類の添付間違い・漏れ確認 | 計算サポート機能により計算ミスを低減 チェック機能により入力漏れを防止 提出必須書類の情報を事前に台紙に印字 |
| ファイリング・保管 | 各種申告書・証明書など 仕分けやファイリング | 原本保管が必要な証明書のみ保管 申告データは印刷不要 |
| 年調データ作成 | 手作業で作成または直接給与計算ソフトに入力 | システムから出力したデータを給与計算システムに取込 |
| 年調計算 | 給与計算システムで計算 | 給与計算システムで計算 |
| 稼働・費用 | 事前準備や申告内容確認、データ化、ファイリングなど担当者の稼働のほか印刷費、郵送費などが発生 | リーズナブルな利用料金 担当者の稼働や印刷費、郵送費などを大幅削減 |
年末調整電子化のメリット

義務化対象外の企業でも年末調整手続きを電子化することで、業務効率化やコスト削減といった多くのメリットがあります。
年末調整手続きの電子化で従業員が得られるメリット
1.手続きの簡素化
年末調整の電子化により、控除証明書などの必要書類をオンラインで簡単に取得し、年末調整システムへ直接入力するため、紙の書類へ記入したり、郵送・持参したりする手間が省けます。また、スマホ対応のシステムなら、いつでもどこでも手軽に手続きすることが出来ます。
2.計算ミスの防止
税額や控除額などの計算はシステムで自動計算されるため、計算ミスがなくなります。結果、修正・再提出の手間を削減することができます。
3.修正作業のしやすさ
提出したデータは電磁的に保存されるため、確認や修正が必要になった場合、容易にデータへアクセスすることができます。これにより、いつでもどこでも申告内容の修正を迅速に行えます。
これらのメリットにより、年末調整手続きがよりスムーズになり、従業員は通常業務に集中する時間が増えます。
年末調整手続きの電子化で企業(総務人事担当者)が得られるメリット
1.業務効率化(働き方改革・テレワーク勤務などに有効)
書類の配布や回収、申告内容の確認といった作業が不要になります。これにより、担当者の業務負担が軽減され、他の業務に集中する時間が増えます。また、税額や控除額の計算は自動計算されるため、計算や転記ミスを防止できます。
2.ペーパーレス化によるコスト削減
書類の印刷や郵送、保管にかかる費用が不要になります。また、紙の保管スペースを節約できるため、オフィス内スペースの有効利用につながります。なお、民間企業が提供する電子年末調整サービスを利用すると費用が発生しますが、作業時間分の人件費や経費面からみて、総合的にコストダウンにつながっているケースが多くなっています。
3.提出プロセスの簡略化
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を通じてデータを送信できるため、税務署への書類提出が簡単になります。また、法定調書なども同様に電子化できるため、一括して処理することができます。データを給与ソフトや人事申告ソフトへ連携すると、システム間でデータの引継ぎが可能となり更に業務効率が向上します。
4.コンプライアンス強化
電磁的に保存されたデータは検索や確認が容易なため、監査や税務調査時に迅速な対応ができます。
これらメリットにより、企業はコストを削減し、業務を効率化し、法令遵守を強化できます。電子年末調整システムの導入は、中長期的な業務改善につながるでしょう。
年末調整を電子化する際の注意点

便利な点が多い電子年末調整申告ですが、電子年末調整サービスの選定にあたり注意すべきポイントを解説します。
既存システムとの連携
給与計算ソフトや労務管理システムとスムーズに連携できるサービスを選ぶことが重要です。
例えば、XML形式やCSV形式など、利用中の給与計算ソフトのインターフェイスに合った形式でデータを出力できるサービスを選ぶ必要があります。
システム連携を無視してサービスを導入すると、申告データを取り込めず一から手入力したり、データを変換したりすることになり、無駄な手間や費用が生じます。
電子年末調整サービスの費用に注意!
電子年末調整サービスの種類は様々で、費用面でも注意が必要です。
国税庁が提供する「年調ソフト」のように無料で利用できるサービスもあれば、クラウドサービスで従量課金制または月額・年額の固定料金制のサービスも数多く存在します。
また、検討中のサービスが従業員規模に適しているかどうかを見極める必要もあります。一見高額に見える年額プランが、総合的に見れば月額プランよりも割安になるケースや、従業員数に合わせて従量課金制で柔軟に対応したいケースなど、選ぶプランやオプションによって費用が大きく異なるため、自社の規模や必要な機能に応じたサービス選びが大切です。
鈴与シンワート株式会社の「S-PAYCIAL with 電子年調申告」は従量課金制で、一人当たり350円と大変リーズナブルな料金で手軽に始められる点がポイントです。(初期費用、基本料金は除く)
電子年末調整サービス比較
電子年末調整サービス導入には、少なからず費用がかかるため慎重に選びたいところです。そこで、国税庁が提供する「年調ソフト」と民間クラウドサービスの比較を紹介します。
1.費用
| 年調ソフト | ・国税庁が提供する無料の年末調整ソフトウェア ・基本的な年末調整業務(源泉徴収票や法定調書の作成)に対応 |
| 民間クラウドサービス | ・有料のサービスが多く、基本料金や従量課金など規模や機能に応じて費用がかかる ・無料トライアルが提供される場合もある |
2.機能
| 年調ソフト | ・年末調整の基本的な機能(源泉徴収票や控除証明書の電子化、法定調書の提出など)を網羅している ・それ以外の労務管理機能や給与計算、勤怠管理との連携はない |
| 民間クラウドサービス | ・申請状況の確認や提出内容の確認が可能 ・年末調整のほか、給与計算、勤怠管理、人事労務管理など多機能を統合したソリューションを提供する場合が多い ・API連携や他の業務システムとのデータ連携も可能 |
3.サポート体制
| 年調ソフト | ・サポートが限定的 ・基本的に自力での利用が求められる |
| 民間クラウドサービス | ・一般的に導入後のカスタマーサポートや、システムトラブル時のサポートが充実している ・電話やチャットなど様々な手段でのサポートが用意されていることが多い |
4.導入・運用
| 年調ソフト | ・利用者それぞれの端末にインストールが必要 ・比較的シンプルで利用しやすい設計 |
| 民間クラウドサービス | ・初期設定や他システムとの連携準備などが必要 ・PC・スマホ・タブレットでオンラインから申請可能 |
従業員の申請作業は、「年調ソフト」でも民間クラウドサービスでも負担を軽減することができます。
「年調ソフト」は、従業員数が少なくかつ電子年末調整サービスに費用をかけたくない企業におすすめです。
総務人事担当者の業務負担軽減を優先させるのであれば、機能やサポート体制が充実した民間クラウドサービスがおすすめです。
もしくは、「年調ソフト」を活用しながら足りない部分を民間クラウドサービスで補うというケースもあります。その場合、「年調ソフト」と民間クラウドサービスが連携可能であることが極めて重要なポイントです。いずれにしても、自社の年末調整業務における課題を明確にした上で、必要な機能を兼ね揃えているサービスを選択することが重要です。
年末調整業務電子化への移行は
「S-PAYCIAL with 電子年調申告」
がおすすめ!
鈴与シンワートの「S-PAYCIAL with 電子年調申告」は、年末調整申告をPC・スマホ・タブレットからいつでもどこでも安心・便利に申請できるクラウドサービスです。
年末調整申告に特化したクラウドサービスで、充実した機能で総務人事担当者の業務負担軽減に貢献します。
具体的なおすすめポイントを紹介します。
「S-PAYCIAL with 電子年調申告」をおすすめする3つのポイント!
1.リーズナブル
「S-PAYCIAL with 電子年調申告」の料金体系は、初期費用、基本料金の他に従量課金制で従業員数によって変動します(利用料金350円/人)。一括支払プランや月額・年額固定制の他サービスに比べて、初期投資を抑えることができるので、導入時の負担を軽減し、中小企業やスタートアップにも利用しやすいサービスです。
2.リアルタイム管理
「S-PAYCIAL with 電子年調申告」は、従業員ごとの申告状況をリアルタイムで確認できるため、スムーズに進捗管理ができます。期限内に申告完了させるように従業員へ催促するのは労力を要する作業ですが、管理画面から進捗状況を管理でき、メール等で声掛けや差し戻しができる点が非常に魅力的なポイントです。
3.利便性
電子年調申告の作成方法はサービスによって異なります。
例えば「はい/いいえ」の選択やリストから選択して作成するアンケート式や、項目が一覧表示され穴埋め式で入力する一覧形式などがあります。
「S-PAYCIAL with 電子年調申告」は、後者の一覧形式を採用しており、入力箇所が最低限で直感的に分かりやすい画面設計です。申告の必要がない箇所をスキップすることも簡単です。
「S-PAYCIAL with 電子年調申告」は、従業員と総務人事担当者とも使いやすく業務負担の軽減に貢献するクラウドサービスです。
拡張機能でもっと便利に!
S-PAYCIALシリーズを併せて利用することで、よりスマートに業務の効率化を図れます。
・「S-PAYCIAL with 電子給与明細」・・・給与明細・賞与明細・源泉徴収票をPC・スマホ・タブレットからいつでもどこでも閲覧できるWeb給与明細サービスです。
紙の明細を発行する場合に比べ、業務時間とコストを大幅に削減できるほか、全従業員へ明細同時発行、安心・安全な個人情報の一元管理など多くのメリットがあります。
・「S-PAYCIAL with 電子人事申告」・・・紙で回収していた入社手続き書類や身上変更時の申請などをペーパーレス化し、書類回収の手間や内容の確認、郵送コストなどを大幅に削減することが可能です。「S-PAYCIAL with 電子年調申告」との連携で、申告書の作成もより簡素化されます。
年末調整電子化の義務化のまとめ

年末調整は、税制改正の影響を受けやすく、改正内容を把握した上で膨大な作業量をこなす必要があり、とても労力を要する業務です。
少しでも業務負担を軽減するためには電子化がおすすめですが、電子化を進めるにあたり年末調整における自社の課題を明確にしたうえで導入を検討することが重要です。
会社の規模や従業員数に見合った、自社の課題を解決できるサービスを選べるといいですね。
よくある質問(FAQ)
Q1. 年末調整の電子化は義務ですか?
A. いいえ(任意)です。ただし、2年前に100枚以上の法定調書を提出している企業は電子化が義務化されます。
令和9年1月以降は、電子化が義務となる基準年の法定調書提出枚数が「100枚以上」から「30枚以上」に引き下げられるため、
昨年まで義務化の対象外だった企業も義務化の対象となる可能性が出てきます。
Q2. 年末調整の電子化に関する国税庁のガイドラインはどこで確認できますか?
A. 国税庁公式サイトの「年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するよくある質問(FAQ)」で確認できます。
URL:https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho_03.htm
Q3. 電子化しても紙が必要な書類はありますか?
A. あります。例として国外居住親族に係る親族関係書類・送金関係書類、勤労学生に該当する旨の証明書等は書面で提出又は提示する必要があります。
Q4. 国税庁が提供する「年調ソフト」と民間クラウドサービスは何が違うの?
A. 「年調ソフト」は無料で利用できます。一方、民間クラウドサービスは有料のサービスが多く基本料金や従量課金など規模や機能に応じて費用がかかりますが、
他システムとのデータ連携やサポート体制が充実しており、年末調整担当者の運用負荷や人的コストを大幅に抑えられます。
-
第11回年末調整電子化の義務?対象企業・メリット・電子化のポイントを解説!
-
第10回ERP(企業資源計画)とは?
-
第09回給与明細を電子化して得られるメリットとは?
-
第08回インボイス制度とは?
-
第07回クラウドサービス型勤怠管理システムの機能・長所とは?
-
第06回残業を削減するためにはどんな取り組みが有効なの?③
-
第05回残業時間を削減するためにはどんな取り組みが有効なの?②
-
第04回残業を削減するためにはどんな取り組みが有効なの?①
-
第03回勤怠管理システム導入で使える補助金・助成金とは?
-
第02回2024年建設業の働き方改革で変わる勤怠管理のポイントとは?
-
第01回国土交通省の i-Constructionとは?