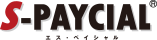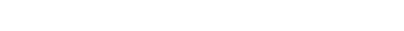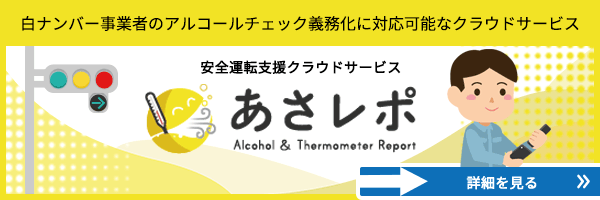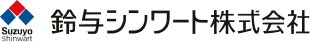S-PAYCIAL コラム
人事・会計の専門家が執筆した
仕事に役立つ情報満載のコラムです

タグクラウド
コラムリスト

(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。
1966年、東京都大田区生まれ。早稲田大学理工学部卒業後、サービス業にて人事 ・管理業務に従事後、現職。クライアント先の人事制度、賃金制度、退職金制度 をはじめとする人事・労務の総合コンサルティングを担当し、複数社の社外人事 部長・労務顧問を兼任する。経営者の視点に立った論理的な手法に定評がある。

クライサー税理士法人 代表 亀戸本店所長 https://www.ishida-tax.net/
明治大学付属明治高等学校、明治大学商学部産業経営学科を卒業。
在学中から税理士を目指し、都内の税理士法人にて、税理士業務全般に従事。
平成23年に石田税務会計事務所を開設。
平成28年より税理士法人化し、名称をクライサー税理士法人へと変更する。
財務面と経営者の視点の両方を兼ね揃えた提案に定評があり、顧問先にじっくりと向き合ったサービスを提供している。
また、仮想通貨に関連する税務業務にいち早く取り組んでおり、独自のサービスも展開している。
(https://www.bitcoin-tax-taisaku.com/)

溝口知実 氏
特定社会保険労務士。溝口労務サポートオフィス代表。千葉県出身。大学卒業後、IT企業の人事労務経理業務、公的年金相談のスーパーバイザー、社会保険労務士事務所勤務などを経て、平成26年溝口労務サポートオフィスを開業。主な業務は中小企業の労務管理全般にわたる相談、コンサルティング、就業規則の作成・改訂など。社会保険労務士10年以上のキャリアを活かし、お客様の発展のために、生き生きと元気なヒトと会社、社会づくりに貢献することを目指し奮闘中。
https://www.mizoguchi-sr-office.jp/

(株)G-flat代表取締役。1981年、北海道札幌市生まれ。
札幌大学経営学部卒業後、大手不動産会社と大手求人メディア企業で営業職に従事。
その後、スタートアップから上場企業までさまざまな規模の企業の人事部マネージャー職にて、給与・人事考課・制度設計など幅広い業務に従事した後、現職に就任。学校法人や上場企業から依頼を受け、キャリアや人材育成などの特別講師を務めるなど、ポートフォリオワーカーとして幅広い事業を手掛けている。

1964年生まれ、広島大学法学部卒。労働組合が経営に与える影響が極めて大きい航空業界で、25年間にわたり、経営管理職と労働組合役員の双方の立場から、1000回以上の労使交渉に臨むという経験を持つ、異色のコンサルタント。本社部門では、グループの経営企画を策定・推進するリーダーのひとりとして活躍。現場では、数百名のパイロットのマネジメントを経験。「社員が社長の思いを汲み取り、自律的かつ機動的に働く現場を育成したい」という信念で、顧客の課題に向き合っている。

ITS社会保険労務士法人 代表
社会保険労務士。情報処理技術者(ITストラテジスト、プロジェクトマネージャ、アプリケー ションエンジニア)。
メーカー系IT企業にて人事業務のシステムコンサルタントに従事。大規模から中小規模まで多くの企業に対し、人事業務における業務コンサルティングからシステムの導入・運用保守まで一貫した対応を多数実施する。
その後、社会保険労務士として現職に至る。労務相談や教育講師の他、電子申請、給与計算などの領域にてITを活用した効率化をご提案する社会保険労務士として活躍中。
このコラムでは、社労士とシステムコンサルの視点にて、労務管理の様々なテーマを取り上げていきたいと思います。
https://it-sharoushi.jp/
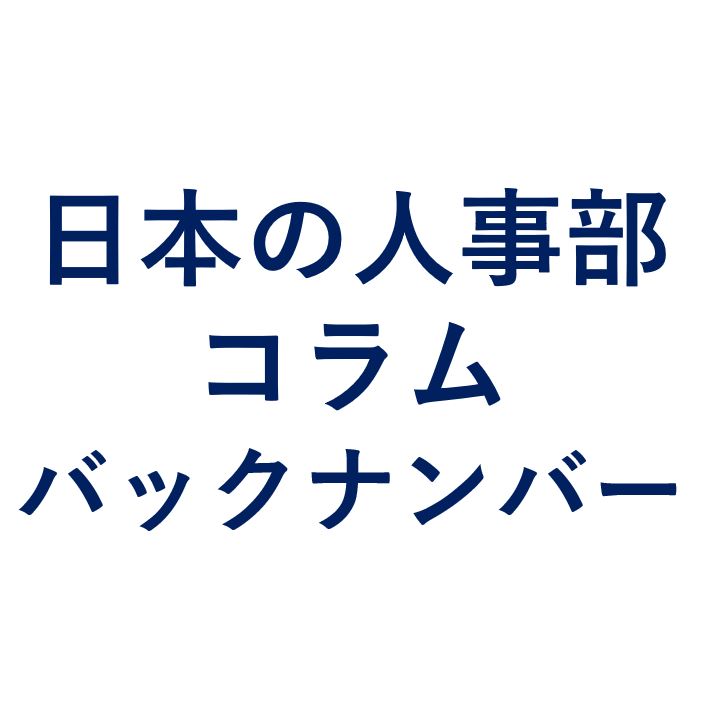
川島孝一氏が「日本の人事部」に寄稿したコラムのバックナンバーを掲載します

やまだ社会保険労務士事務所
所長
特定社会保険労務士
1965年生まれ 東京都出身。大学卒業後、総合病院勤務を経て14年間、健康保険組合に従事。資格得喪・保険給付業務、制度構築、システム開発を経て、2004年10月横浜市緑区にて、やまだ社会保険労務士事務所を設立。
2005年5月東京都町田市に事務所移転。
「困った」を「良かった」とすることをコンセプトに労務管理におけるプライマリケアサービスを提供。
賃金設計、労災、是正勧告、行政対応、個別紛争解決を得意とする。 趣味:天体観測、ヨットレース、カヤック、キャンプ。

鈴与シンワート マーケティング担当が、人事・給与・勤怠業務と財務・会計業務ソリューションに関するコラムを不定期に更新していきます。

鈴与シンワート株式会社 ビジネス・プロセス・サービス事業部 営業部 飯嶋大樹
1987年埼玉県生まれ、高校時代はバスケットボール部の活動に打ち込み、大学では環境・情報システムを専攻していました。
現在は営業マンとして日々、各社人事部のご担当者様と会話をし、人事・給与・就業に関してシステム提案をしながら、人事・総務などの業務全般の勉強をさせて頂いております。
その中で身近な人事労務などの法改正や社内制度などをテーマにしたコラムを執筆していきたいと、思っております。
どうぞよろしくお願い致します。

税理士。東京外国語大学卒業。 TACの全日本答練「財務諸表論」「法人税法」を全国1位の成績で、税理士試験に合格。直後に出産。育児と両立させるため、1日3時間だけの会計事務所からスタートし、現在は全員女性だけのスタッフ22名、一部上場企業の子会社やグローバル企業の日本子会社などをクライアントにもつ。 ミャンマーに会計サービスの会社を設立し、海外進出支援にも力をいれている。 著書に「小さな会社のための総務・経理の仕事がわかる本」「小さな起業のファイナンス」いずれもソーテック社刊。「51の質問に答えるだけですぐできる『事業計画書』のつくり方」日本実業出版社刊。「トコトンわかる株式会社のつくり方」新星出版社刊。「世界一ラクにできる確定申告」技術評論社刊。「一生食っていくための士業の営業術」中経出版など。 その他、「経理ウーマン」「デイの経営と運営」など雑誌への寄稿や、商工会議所、中小企業投資育成株式会社、日本政策金融公庫などでの、セミナー実績も多数。
原&アカウンティング・パートナーズ代表。

吉政創成株式会社の代表取締役、一般社団法人PHP技術者認定機構 代表理事、BOSS-CON JAPANの理事長、Rails技術者認定試験運営委員会の委員長 を兼任。
その他、IT市場動向や人材関連の講演が年間で30回以上、月刊連載のコラムが15本あります。

税理士。1975年埼玉生まれ、山口・群馬・東京育ち。98年日本大学文理学部心理学科卒業。中央競馬ピーアールセンター(JRA外郭団体)、落合会計事務所、KCCSマネジメントコンサルティング(アメーバ経営/京セラグループ)勤務後、08年に独立開業。「会計を通じて人を幸せにする」をモットーに中小企業向けの業績改善・経営指導に力を入れている。研修講師『キャッシュフロー重視の財務体質改善講座』(中小企業大学校)、『月次決算の活かし方』(エヌ・ジェイ出版販売)、執筆記事『バンカーのための数値力強化メソッド』(バンクビジネス)『減価償却の改正内容と経理・税務のポイント』(企業実務)『ひとり経理の「困った!」「弱った!」解消セミナー』(経理ウーマン)など。