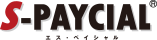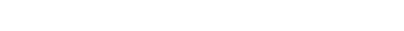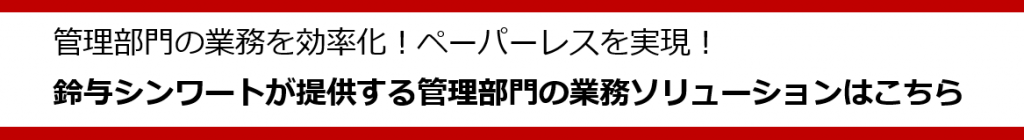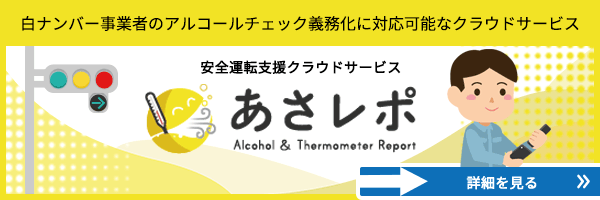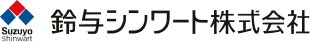美術品に関する会計処理と税務
目次
企業が、絵画などの美術品を購入した際の会計処理について解説いたします。
1.美術品とは何か
美術品とは、具体的には例えば以下のものが該当します。
古美術品・古文書・出土品・遺物等・絵画、彫刻、工芸品、書画、骨とう

2.勘定科目
原則的には、「工具器具備品」として処理することになります。ただし、取得価額(運送費等の付随費用を含む。)が10万円未満の場合には、税法の基準により「消耗品費」として処理するのが一般的です。
3.減価償却資産かどうか
減価償却とは、時の経過によって資産の価値が減少する部分を費用化するための科目です。したがって、その美術品が時の経過によって価値が減少するのかどうかで減価償却資産に該当するか否かが決まります。
国税庁からは、以下の基準が示されております。(以前存在していた美術年鑑基準は廃止されました。)
「2015年1月1日以後に取得した美術品は、取得価額が1点100万円未満であれば原則として減価償却することが出来る。」

上記の通達により、1点100万円以上の美術品は原則として、減価償却することができません。
4.3、の例外
ただし、100万円以上の美術品であっても、時の経過によって価値が減少することが明らかであれば、減価償却することが可能です。具体的には、以下の3つが示されています。
① 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。 (ただし、ガラスケース等に収納されているなどの配慮がされている場合を除く。) ② 移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。 ③ 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。 |
5.耐用年数
美術品を減価償却する場合の耐用年数について、耐用年数表の器具備品「11.前掲以外-その他-その他」の5年を適用しているケースをしばしば目にしますが、正しくは、
耐用年数表の「器具及び備品」の「室内装飾品」を適用して、以下の通りとします。
・室内装飾品のうち主として金属製のもの・・・15年
・室内装飾品のうちその他のもの・・・・・・・8年
例えば、絵画であれば、上記のより、耐用年数8年を適用するのが妥当と考えられます。
以上 美術品の処理について取り上げました。
国税庁より、100万円基準と言う金額基準が示されましたが、「時の経過によって価値が減少することが明らか」かどうかによって取り扱いが決まるため、最終的には個々の事例ごとに判断することになります。その都度、顧問税理士へお問い合わせください。
鈴与シンワート株式会社が提供する人事・給与・勤怠業務と財務・会計業務ソリューションはこちらからご覧ください。
-
第59回ペットに関する会計処理について
-
第58回控除対象外消費税の会計処理
-
第57回ソフトウェアに関する経理処理①について
-
第56回新リース会計について①
-
第55回税金の処理について
-
第54回グループ通算制度について②
-
第53回グループ通算制度について①
-
第52回美術品に関する会計処理と税務
-
第51回不動産取得時の会計処理の注意点①
-
第50回支度金に関する会計処理と税務
-
第49回損害賠償金の会計・税務② ~取り扱い(具体例)と消費税の取り扱いについて~
-
第48回損害賠償金の会計・税務①
-
第47回永年勤続表彰に関する経理処理について
-
第46回一括売買した土地・建物の内訳が不明な場合の按分について
-
第45回ストックオプション制度について②
-
第44回ストックオプション制度について①
-
第43回インボイス制度の実務③インボイス制度における税額計算
-
第42回インボイス制度の実務②インボイス制度における税額計算
-
第41回インボイス制度の実務①インボイスの記載事項 その3
-
第40回インボイス制度の実務①インボイスの記載事項 その2
-
第39回インボイス制度の実務①インボイスの記載事項 その1
-
第38回暗号資産(仮想通貨)に関する経理処理について④
-
第37回リース資産の減損会計について
-
第36回減損会計について
-
第35回事業譲渡に伴う資産除去債務の処理方法について 考え方①
-
第34回貸倒引当金についての会計税務
-
第33回ポイント引当金について
-
第32回特別損失に関する会計処理
-
第31回のれんに関する会計処理
-
第30回税効果会計①について
-
第29回自己株式に関する経理処理について②
-
第28回会計と税務の相違点について①
-
第27回生命保険に関する経理処理について(その4)
-
第26回生命保険に関する経理処理について(その3)
-
第25回役員賞与に関する法人税および消費税の取扱に関する処理①について
-
第24回補助金・助成金・給付金に関する法人税および消費税の取扱に関する処理について
-
第23回地代家賃に関する法人税および消費税の取扱に関する処理について
-
第22回切手代等に関する会計処理ならびに法人税および消費税の取扱に関する処理について
-
第21回仮想通貨に関する経理処理について③
-
第20回不動産取引に関する経理処理①について
-
第19回合併に関する経理処理①について
-
第18回リース取引に関する経理処理について①
-
第17回本店・支店取引に関する経理処理(決算)について②
-
第16回本店・支店取引に関する経理処理について①
-
第15回減価償却に関する経理処理について②
-
第14回減価償却に関する経理処理について①
-
第13回現金・小口現金に関する経理処理について
-
第12回自己株式に関する経理処理について
-
第11回手形に関する経理処理について①
-
第10回研究開発費に関する経理処理について
-
第09回仮想通貨に関する経理処理について②
-
第08回仮想通貨に関する経理処理について①
-
第07回有価証券に関する経理処理について(売買目的有価証券 編)
-
第06回資産除去債務に関する経理処理について
-
第05回生命保険に関する経理処理について(その2)
-
第04回生命保険に関する経理処理について(その1)
-
第03回繰延資産についての経理処理
-
第02回税込経理と税抜経理の処理の注意点~消費税の経理処理について~
-
第01回確定給付年金と確定拠出年金の会計処理について