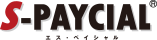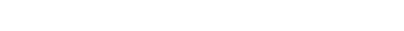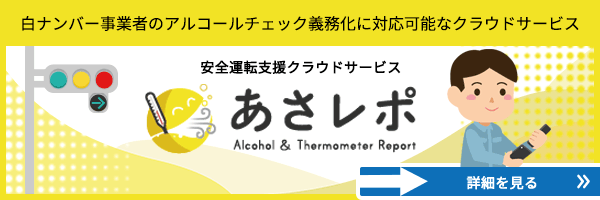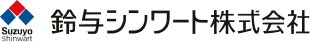退職金の税務計算
目次
さまざまな会社の給与明細を見ていると、たまに退職金を給与に上乗せして一緒に支払ってしまっている明細書に出くわすことがあります。担当者に確認すると、給与に合算するのは、「振込先は一緒だから。」「まとめた方が計算が楽だから。」などの理由があるようです。
税務上は、「給与所得」と「退職所得」はまったく異なるものであり、退職所得は、給与所得に比べて税務上優遇されています。給与と退職金をそれぞれ計算し、振込の手間や手数料を省くためにまとめて支払うのであれば問題はありません。しかし、給与に合算して計算してしまうのは、必要以上の税金を徴収されることにつながり、本人にとっても不利益になります。
今回は、退職金の税金計算についてみていきたいと思います。
退職金とは
「退職所得」とは、会社を退職をしたことにより勤務先から受ける退職金などの所得をいいます。会社から支給される退職金だけでなく、確定給付企業年金契約に基づいて生命保険会社や信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や、賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金なども、すべて退職所得に該当します。
退職金に課税される所得税の計算方法
退職金に課税される所得税の計算方法は、「退職所得の受給に関する申告書」が提出されているか否かで計算方法が変わってきます。一般的な従業員に支給する退職所得に対する所得税の計算方法は、次のようになります。
1.申告書が提出されている場合
退職所得の受給に関する申告書が提出されていると、勤続年数によって、退職所得控除の金額が変わります。
退職所得控除の金額は、「20年以下」と「20年超」との間でラインが設定されています。勤続年数とは、原則として、退職手当等の支払者の下で退職の日まで引き続き勤務した期間の年数です。
勤続期間に1年に満たない端数があるときは、「1年」に切り上げられる点はぜひ押さえておいてください。
次に、勤続年数に応じて、次の計算により退職所得控除額を算出します。
【退職所得控除額の計算式】
勤続年数(=A) 退職所得控除額
・勤続20年以下 40万円×A
・勤続20年超 800万円+70万円×(A-20年)
つまり、上記の計算式の金額以下であれば、全額「非課税」ということになります。
退職金の支給額から上記で計算した退職所得控除額を控除し、その残額の「2分の1」(1,000円未満の端数は切り捨てます。)が課税退職所得金額になります。
課税退職所得金額が計算できたら、次は所得税の金額を計算します。計算式の最後にある「102.1%」は「復興特別所得税」の分になります。
【退職所得の源泉徴収税額の計算式】
課税退職所得金額(A) 所得税率(B) 控除額(C) 税額=((A)×(B)-(C))×102.1%
・195万円以下 5% 0円 (A×5%)×102.1%
・195万円超 330万円以下 10% 97,500円 (A×10%- 97,500円)×102.1%
・330万円超 695万円以下 20% 427,500円 (A×20%- 427,500円)×102.1%
・695万円超 900万円以下 23% 636,000円 (A×23%- 636,000円)×102.1%
・900万円超1,800万円以下 33% 1,536,000円 (A×33%-1,536,000円)×102.1%
・1,800万円超4,000万円以下 40% 2,796,000円 (A×40%-2,796,000円)×102.1%
・4,000万円超 45% 4,796,000円 (A×45%-4,796,000円)×102.1%
なお、源泉徴収税額の最終の端数は、1円未満を切り捨てます。
それでは、実際の具体的な計算方法をみていきましょう。
【例 退職金の支給額が800万円、勤続年数が10年2か月の場合】
1)勤続年数 1年未満の端数は1年に切上げるので、「11年」
2)退職所得控除額 40万円×11年=440万円
3)課税退職所得金額 (800万円-440万円)×1/2=180万円
4)税額 180万円×5%×102.1% =91,890円
したがって、この場合の所得税(復興特別所得税を含む)の源泉徴収税額は、「91,890円」になります。
2.申告書の提出がない場合
退職所得の受給に関する申告書が提出されていない場合には、退職手当等の金額に「20.42%」の税率を乗じて計算した所得税(復興特別所得税を含む)を源泉徴収します。
この場合は退職金がどんなに少なくとも、源泉所得税が発生するというわけです。
退職所得の受給に関する申告書が提出されている場合とされていない場合の、源泉所得税の金額を比較してみましょう。
例えば、さきほどの例のように退職金の支給額が800万円の場合は、
800万円×20.42%=1,633,600円
となり、源泉徴収する所得税(復興特別所得税を含む)の額は「1,633,600円」になります。
同じ支給額でも、源泉徴収する金額にだいぶ違いが出ることがわかります。
退職金には、社会保険料や雇用保険料はかかりませんが、課税退職所得金額がある場合には、住民税も源泉徴収をする必要があります。
会社によっては、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がされていないにもかかわらず、源泉徴収をしていないケースもあるようです。退職金の計算は給与や賞与とはまったく異なることを理解いただき、正しく計算するようにしましょう。
-
第117回雇用保険の加入要件
-
第116回年収の壁・支援強化パッケージ
-
第115回社会保険の扶養家族の年収の壁
-
第114回令和5年度の最低賃金
-
第113回平均賃金の計算方法
-
第112回有給休暇の買上げ
-
第111回運賃改定と社会保険
-
第110回現物給与の価額変更
-
第109回賃金のデジタル通貨払い
-
第108回令和5年度の雇用保険の料率
-
第107回賃金請求権の消滅時効の延長
-
第106回月60時間超の残業の割増率と代替休暇
-
第105回令和5年からの源泉徴収事務の変更点
-
第104回育児休業の社会保険料免除
-
第103回デジタル通貨での給与の支払い
-
第102回2022年10月からの給与計算の注意点
-
第101回振替休日と代休の違い
-
第100回産後パパ休暇と給与計算
-
第99回社会保険の定時決定~その2
-
第98回社会保険の定時決定~その1
-
第97回雇用保険の料率変更
-
第96回定年延長と退職金
-
第95回夜勤シフトの割増賃金
-
第94回休業補償と休業手当
-
第93回社会保険の適用拡大について
-
第92回令和3年の年末調整
-
第91回兼業している65歳以上の方の雇用保険
-
第90回個人型確定拠出年金(iDeCo)
-
第89回社宅家賃や社員旅行の積立金
-
第88回感染対策費用の課税・非課税
-
第87回兼業、副業の時間外手当
-
第86回2以上事業所勤務者の社会保険料
-
第85回有給休暇と残業手当
-
第84回在宅勤務手当の非課税計算
-
第83回延長された社会保険の特例改定
-
第82回育児・介護休業法の改正
-
第81回年末調整のイレギュラー対応
-
第80回年末調整の変更点~その2
-
第79回年末調整の変更点~その1
-
第78回厚生年金保険保険料の上限引き上げ
-
第77回新型コロナウイルスによる社会保険標準報酬月額の特例改定
-
第76回寡婦控除の見直し
-
第75回住民税の特別徴収
-
第74回在宅勤務時の労働時間と割増賃金
-
第73回高年齢労働者の雇用保険料免除の廃止
-
第72回休業手当の計算方法
-
第71回源泉所得税の仕組み
-
第70回時間単位の有給休暇付与
-
第69回短時間労働者の社会保険の適用拡大
-
第68回60時間超の残業の割増率の猶予措置廃止
-
第67回フレックスタイム制の改正と残業代
-
第66回健康保険の加入資格と保険料
-
第65回厚生年金保険の加入資格と保険料
-
第64回介護保険料を徴収するタイミング
-
第63回社会保険における賃金とは
-
第62回労働保険における賃金とは
-
第61回労働基準法における賃金とは
-
第60回出来高払い制の残業代
-
第59回休業手当の計算方法
-
第58回賞与における所得税の計算
-
第57回年末調整(住宅ローン控除)の実務
-
第56回年末調整の変更点
-
第55回社宅制度と労働保険料
-
第54回社宅制度と社会保険料
-
第53回住宅手当と社宅貸与の違い
-
第52回退職金の税務計算
-
第51回賃金支払いの5原則~その4(最終回)
-
第50回賃金支払いの5原則~その3
-
第49回賃金支払いの5原則~その2
-
第48回賃金支払いの5原則~その1
-
第47回時給者の有給休暇の賃金の計算方法
-
第46回割増賃金の基礎となる賃金
-
第45回年末調整の留意点~その2
-
第44回年末調整の留意点~その1
-
第43回退職者の住民税
-
第42回労働時間の端数処理
-
第41回入社した従業員がすぐに退職したとき
-
第40回賃金から控除できる項目と労使協定
-
第39回1か月60時間超の残業の割増率と代替休暇
-
第38回退職者の社会保険料徴収とタイミング
-
第37回雇用保険料率の改定と変更のタイミング
-
第36回最低賃金の仕組み
-
第35回毎月の給与からの源泉所得税の徴収
-
第34回65歳以上の従業員に対する雇用保険の法改正
-
第33回今年の年末調整の留意点
-
第32回年末調整における海外居住の扶養家族
-
第31回年末調整におけるマイナンバーの取扱
-
第30回従業員が死亡したとき
-
第29回雇用保険料と介護保険料の免除
-
第28回企画業務型裁量労働制と割増賃金の考え方
-
第27回事業場外労働に関するみなし労働時間制度の考え方
-
第26回専門業務型裁量労働制と割増賃金の考え方
-
第25回1週間単位の変形労時間制度
-
第24回フレックスタイム制の労働時間制度
-
第23回1年単位の変形労時間制度
-
第22回1か月単位の変形労時間制と残業代の関係
-
第21回管理職への残業代の支払い
-
第20回今年の年末調整で昨年から変更になった点
-
第19回社会保険料の仕組みと変更時期
-
第18回通勤費の決め方と非課税限度額
-
第17回報奨金の現金支給や現物給与
-
第16回徹夜勤務や遅刻をした日の残業代の支払い
-
第15回有給休暇の付与と消滅
-
第14回給与の支給日の決め方やその変更
-
第13回給与計算の誤入力を修正するときの注意点
-
第12回標準報酬月額の随時改定
-
第11回年間の給与計算の流れ
-
第10回年末調整の後の諸手続き
-
第09回離婚時の年金の分割制度
-
第08回年末調整その1~年末調整の意味と対象者~
-
第07回遅刻をした日に残業をしたときの計算方法
-
第06回就業規則と給与計算の関係
-
第05回給与から引かれるものは?
-
第04回残業代を正しく計算するための基礎知識
-
第03回賞与の支給と給与計算
-
第02回産前産後休業や育児休業の仕組みと社会保険料
-
第01回消費税増税で変わる通勤手当と社会保険料