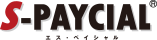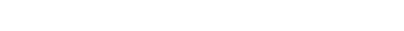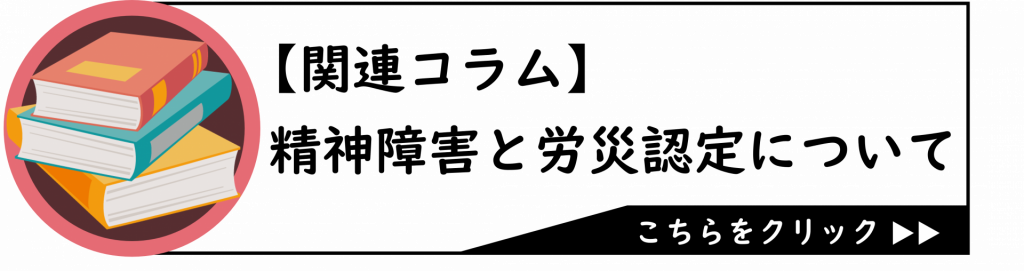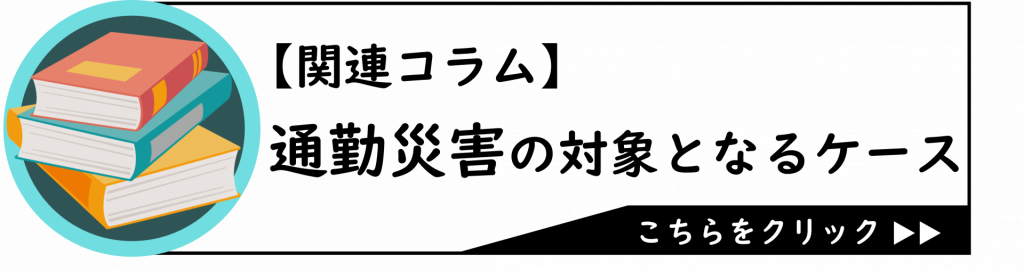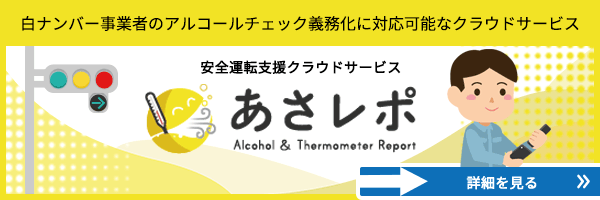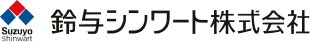どんな業種でも起こる労働災害の申請手続き
目次
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課が平成26年1月に発表した『平成25年における労働災害発生状況(速報)』によると、製造業や建設業において多くの労働災害が発生しています。これらの業種は、労働災害が発生しやすい業種だというのは簡単にイメージができると思います。
| 業種 | 平成25年(1月~12月) | 平成24年(1月~12月) | 対24年比較 | |||
| 死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 全産業 | 105,747 | 100.0 | 107,766 | 100.0 | -2,019 | -1.9 |
| 製造業 | 24,518 | 23.2 | 25,814 | 24.0 | -1,296 | -5.0 |
| 鉱業 | 224 | 0.2 | 190 | 0.2 | 34 | 17.9 |
| 建設業 | 15,762 | 14.9 | 15,626 | 14.5 | 136 | 0.9 |
| 交通運輸事業 | 2,837 | 2.7 | 2,834 | 2.6 | 3 | 0.1 |
| 陸上貨物運送事業 | 12,870 | 12.2 | 12,615 | 11.7 | 255 | 2.0 |
| 港湾運送業 | 273 | 0.3 | 322 | 0.3 | -49 | -15.2 |
| 林業 | 1,642 | 1.6 | 1,800 | 1.7 | -158 | -8.8 |
| 農業・畜産・水産業 | 2,497 | 2.4 | 2,657 | 2.5 | -160 | -6.0 |
| 第三次産業 | 45,124 | 42.7 | 45,908 | 42.6 | -784 | -1.7 |
しかし、労働災害が発生するのは、製造業や建設業だけではありません。昨年は、第三次産業と呼ばれる業種でも労働災害によって45,124人の死傷者を出しています。
あまり労働災害がおきないイメージのある第三次産業ですが、この中には近年増加している精神疾患による療養や自殺も含まれます。
| 業種 | 平成25年(1月~12月) | 平成24年(1月~12月) | 対24年比較 | |||
| 死傷者数(人) | 構成比(%) | 死傷者数(人) | 構成比(%) | 増減数(人) | 増減率(%) | |
| 第三次産業 | 45,124 | 100.0 | 45,908 | 100.0 | -784 | -1.7 |
| 商業 | 14,699 | 32.6 | 15,233 | 33.2 | -534 | -3.5 |
| うち小売業 | 11,172 | – | 11,588 | – | -416 | -3.6 |
| 金融・広告 | 1,143 | 2.5 | 1,266 | 2.8 | -123 | -9.7 |
| 通信 | 2,327 | 5.2 | 2,629 | 5.7 | -302 | -11.5 |
| 保健衛生業 | 8,488 | 18.8 | 8,365 | 18.2 | 123 | 1.5 |
| うち社会福祉施設 | 5,806 | – | 5,618 | – | 188 | 3.3 |
| 接客・娯楽 | 7,242 | 16.0 | 7,279 | 15.9 | -37 | -0.5 |
| うち飲食店 | 3,901 | – | 3,816 | – | 85 | 2.2 |
| 清掃・と畜 | 5,445 | 12.1 | 5,257 | 11.5 | 188 | 3.6 |
| 警備業 | 1,280 | 2.8 | 1,216 | 2.6 | 64 | 5.3 |
| その他 | 4,500 | 10.0 | 4,663 | 10.2 | -163 | -3.5 |
通勤災害はもともとあまり業種には関係ありませんが、業務災害であってもどの業種でも発生する可能性があります。経営者や事務担当者は、人が働いている以上どのような業種でも労働災害が発生してしまう可能性があることを理解しておくことが大切です。
長時間労働やパワハラに起因する労働災害が増えている近年では、労働災害の手続き遅れやミスにより被災労働者やその遺族とトラブルになるケースもあります。今回は、労働災害保険の制度や給付の内容の基本的な部分や手続の方法等を紹介します。
<労働災害保険とは>
労働災害保険は
①業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、傷害、死亡等に対して必要な保険給付の実施、
②業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の保護、
の2つを目的としています。そのため、業務上や通勤中の怪我や疾病に対する保険給付だけでなく、社会復帰促進等事業として被災労働者やその遺族に対する資金の貸付なども行っています。
<労働災害保険の保険給付>
業務災害や通勤災害に関する保険給付には、次の7種類があります。
①療養(補償)給付、 ②休業(補償)給付、
③傷害(補償)給付、 ④遺族(補償)給付、
⑤葬祭料、葬祭給付、 ⑥傷病(補償)年金、
⑦介護(補償)給付
通勤災害は労働災害ではないので、基本的には会社に責任はありません。しかし、業務を行うために通勤するのですから、労働災害に準じて保険給付を受けられます。業務災害の場合は( )内もそのまま読み(①なら「療養補償給付」)、通勤災害の場合は( )内をとって読みます(①なら「療養給付」)。
両者は読み方の違いこそあれ、給付の内容は基本的には同一です。
それでは、業務災害や通勤災害が発生してしまった場合に一番利用する頻度が高い「療養(補償)給付」と「休業(補償)給付」を具体的にみていきましょう。
1)療養(補償)給付
労働者が仕事中や通勤中の怪我や、従事している業務が原因で病気になってしまった場合に、それらの治療を行うときは療養(補償)給付が受けられます。
療養(補償)給付は「現物給付」が原則です。このため、労働災害による治療は原則として無料で受けることができます。
実務上よくあるケースが、労働災害だったのに健康保険証を使用してしまうケースです。健康保険証を利用してしまうと、あとで治療にかかった医療費を全額清算する必要があります(通常最初に窓口で3割負担していますので、残りの7割をいったん支払うことになります)。
全額清算した後に労働基準監督署で手続きを行い、支払った金額は最終的には全額還付されます(療養の費用請求)が、手続きの手間と支給決定までに時間がかかります。その間、従業員が治療費を全額負担することになってしまいますので、業務上や通勤中の怪我や病気で病院や薬局を利用した場合は、必ず病院や薬局に業務災害や通勤災害だったことを伝えることが大切です。
療養(補償)給付を受けるための手続きは、「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」を病院へ提出します。院外薬局で薬をもらった場合は、こちらにももう1枚提出します。
一方、いったん負担した治療費の還付を受けようとする場合には、「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」を労働基準監督署に提出します。
2)休業(補償)給付
業務災害や通勤災害によって怪我や病気になってしまい治療のため仕事を休まざるを得ない者に対して休業(補償)給付により、給与の補填が行なわれます。
支給額は、給付基礎日額の100分の60です。給付基礎日額とは、怪我や病気になった日の直近3か月間に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で除した金額(平均賃金)になります。
休業(補償)給付には、3日間の待機期間が設けられています。この3日間は労災保険ではカバーすることができないので、事業主は、労働基準法上の休業補償(平均賃金の100分の60)を支払う必要があります。
一方、通勤災害が原因の場合は、労働災害ではありませんので、待機期間の3日間については労働基準法上の休業補償を行う必要はありません。
3)休業特別支給金について
休業(補償)給付を受ける者には、社会復帰促進事業の一環として休業(補償)給付に給付基礎日額の100分の20に相当する金額が加算されます。
したがって、労災で休業した場合は、休業(補償)給付とあわせて給与の約80%が補償されることになります。
休業(補償)給付と休業特別支給金の手続きは、「休業(補償)給付支給申請書」を会社所在地の労働基準監督署に提出することで、同時に行なえます。
休業が長期間に及ぶ場合は、複数回にわけて申請が可能です。申請日より後の日の請求はできませんので、通常は給与締め日ごとに申請します。
<最後に>
労働災害保険は、保険給付だけではなく社会復帰促進等事業において様々な事業を行っています。もちろん、労働災害を発生させないのがベストですが、万が一、業務災害や通勤災害が起きてしまったときは経営者や事務担当者は迅速な対応が求められます。
手続きの遅れやミスによって余計なトラブルを抱え込まないようにしましょう。
鈴与シンワートでは従業員規模や機能性によって選べる人事・給与・就業・会計システム、自社オリジナルの「人事・給与業務アウトソーシングサービス」、クラウドサービスの「電子給与明細」「電子年末調整」、奉行クラウドと基幹システムの自動連携などを提供しています。
個社特有の課題やご要望にお応えいたしますので、是非お気軽にお問い合わせください。
-
第151回有給休暇取得時の賃金の計算方法
-
第150回深夜業と勤務間インターバル制度
-
第149回フレックスタイム制の休憩時間
-
第148回出来高払制給与の割増賃金
-
第147回令和7年度の最低賃金
-
第146回特定親族特別控除と社会保険扶養家族の認定基準
-
第145回フレックスタイム制の概要と時間外労働
-
第144回兼業や副業の場合の割増賃金と今後の方向性
-
第143回2025年度税制改正について
-
第142回社会保険の報酬と月額変更
-
第141回定額減税の残額の給付
-
第140回社会保険における年収の壁
-
第139回年収の壁の種類と103万円の壁
-
第123回最低賃金の対象となる賃金
-
第138回年収の壁の種類と100万円の壁~103万の壁、130万の壁以外にも「壁」がある~
-
第137回対象者の拡大が見込まれるストレスチェック制度
-
第136回アルバイトの1ヶ月単位変形労働時間制の適用
-
第135回健康保険証の廃止
-
第134回育児介護休業の改正
-
第133回労働時間の適正な管理方法
-
第132回バス運転者の改善基準告示~その3
-
第131回バス運転者の改善基準告示~その2
-
第130回バス運転者の改善基準告示~その1
-
第129回タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示~その2
-
第128回タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示
-
第127回トラック運転者の改善基準告示~その2
-
第126回トラック運転者の改善基準告示~その1
-
第125回運送業における時間外労働の上限規制
-
第124回建設業における時間外労働の上限規制
-
第122回医業における時間外労働の上限規制
-
第121回年次有給休暇と割増賃金
-
第120回会社の管理職と労基法の管理監督者
-
第119回運送業と建設業の労働時間の上限規制
-
第118回給与のデジタル通貨払い~その2
-
第117回給与のデジタル通貨払い
-
第116回障害者雇用率の引き上げ
-
第115回健康経営について
-
第114回社会保険加入の勤務期間要件の変更
-
第113回勤務時間中の喫煙と休憩時間
-
第112回男女の賃金の差異の情報公表~賃金差異の計算方法
-
第111回男女の賃金の差異の情報公表
-
第110回アルコールチェックの義務化
-
第109回新型コロナウイルス感染症の後遺症の労災認定
-
第108回労働時間の判断基準
-
第107回労働時間と休憩時間
-
第106回夜勤シフトと休日の関係
-
第105回有給休暇の買上げ
-
第104回2022年の法改正項目~社会保険の適用拡大と女性活躍法
-
第103回2022年の法改正項目~育児介護休業法の改正
-
第102回2022年の法改正項目~パワーハラスメントの防止対策
-
第101回休憩時間のルール
-
第100回労働者代表の選任
-
第99回令和3年 育児休業法の改正について~その2
-
第98回令和3年 育児休業法の改正について
-
第97回過労死の労災認定基準
-
第96回テレワーク時の労災~通勤災害
-
第95回テレワーク時の労災~その1
-
第94回70歳までの雇用延長~その2
-
第93回70歳までの雇用延長~その1
-
第92回同一労働同一賃金と最高裁判例
-
第91回増加する兼業・副業~その3 通算労働時間の確認方法
-
第90回増加する兼業・副業~その2 労働時間の通算
-
第89回最低賃金の引上げ
-
第88回コロナ感染と通勤災害
-
第87回コロナ感染と労災認定
-
第86回パワハラ防止法~その8
-
第85回パワハラ防止法~その7
-
第84回パワハラ防止法~その6
-
第83回パワハラ防止法~その5
-
第82回パワハラ防止法~その4
-
第81回パワハラ防止法~その3
-
第80回パワハラ防止法~その2
-
第79回パワハラ防止法~その1
-
第78回労働者派遣法の改正~労働者の待遇の情報提供
-
第77回労働者派遣法の改正~その2
-
第76回労働者派遣法の改正~その1
-
第75回1号特定技能外国人の判断基準~その2
-
第74回1号特定技能外国人の判断基準~その1
-
第73回新しい在留資格
-
第72回有期労働契約の解除
-
第71回働き方改革~新36協定の内容
-
第70回働き方改革~36協定の締結内容の変更
-
第69回働き方改革~同一労働同一賃金
-
第68回働き方改革~産業医の活用と機能強化
-
第67回働き方改革~高度プロフェッショナル制度
-
第66回働き方改革~フレックスタイム制の改正
-
第65回働き方改革~その2
-
第64回働き方改革~その1
-
第63回安全衛生管理体制~その2
-
第62回安全衛生管理体制~その1
-
第61回会社が行う健康診断~その2
-
第60回会社が行う健康診断~その1
-
第59回就業規則のいろはのイ
-
第58回労働契約の申込みみなし制度
-
第57回改正労働者派遣法の2018年問題
-
第56回いよいよ始動する無期転換ルール
-
第55回働き方改革を実現するために(その4)
-
第54回働き方改革を実現するために(その3)
-
第53回働き方改革を実現するために(その2)
-
第52回働き方改革を実現するために(その1)
-
第51回病気療養のための休暇や短時間勤務制度
-
第50回年次有給休暇の取得率の向上と一斉付与
-
第49回労働時間等見直しガイドラインの活用
-
第48回テレワークの導入と労働法の考え方
-
第47回管理職と管理監督者の違い
-
第46回同一労働同一賃金の行方
-
第45回時間外労働、休日労働に関する協定の重要性
-
第44回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その5 子の看護休暇等の改正ポイント~
-
第43回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その4 育児介護休業規程の改正ポイント~
-
第42回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その3 子の看護休暇等の改正ポイント~
-
第41回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その2 介護休業の改正ポイント~
-
第40回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その1 育児休業の改正ポイント~
-
第39回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度~その5 高ストレス者への面接指導の方法と注意点~
-
第38回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度~その4 高ストレス者の選定基準と診断結果の通知~
-
第37回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その3 調査票作成編~
-
第36回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その2実施方法編~
-
第35回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 その1
-
第34回在宅勤務制度と事業場外労働の規程例
-
第33回通勤災害の対象となるケース
-
第32回ついに成立した改正労働者派遣法~その3
-
第31回ついに成立した改正労働者派遣法~その2
-
第30回ついに成立した改正労働者派遣法~その1
-
第29回いよいよ通知がはじまるマイナンバー
-
第28回日本で働くことができる外国人
-
第27回いよいよ成立が見込まれる労働者派遣法
-
第26回休職中の社会保険料の取扱いと休職規定サンプル
-
第25回慶弔休暇のルールは就業規則等で明確にしておこう
-
第24回来年1月開始~マイナンバー制度 その3
-
第23回来年1月開始~マイナンバー制度 その2
-
第22回来年1月開始~マイナンバー制度 その1
-
第21回パートタイム労働法の改正と社会保険の適用
-
第20回急増する労務トラブルの解決機関にはどのようなものがあるか
-
第19回精神障害と労災認定
-
第18回解雇は最終手段?
-
第17回今の法律でもできる、成果で従業員を評価する仕組み
-
第16回労働組合のない会社必見!!~労働組合の基礎知識~
-
第15回残業代を定額で支払うのは
-
第14回法改正が続く有期雇用労働者との雇用契約
-
第13回どんな業種でも起こる労働災害の申請手続き
-
第12回賞与を支給すると逆効果??
-
第11回インターン生であれば労働者ではないのか
-
第10回会社に有給休暇を買い取ってもらえるようになる?
-
第09回アルバイトが引きおこす「悪ふざけ」への人事的対応
-
第08回大々的に行われる「ブラック企業」対策