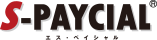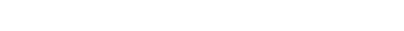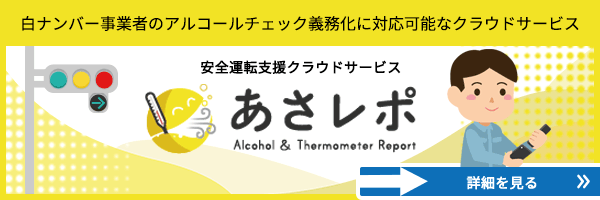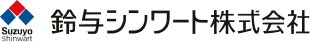定額減税の残額の給付
目次
昨年は、2024年6月1日以降に支払われる給与や賞与に課税される所得税に対して定額減税が行われ、年末調整でも定額減税が行われました。今年に入って、定額減税を引ききれなかった場合の対応について問い合わせが増えています。
今回は、年末調整後に定額減税額が残った場合の対応についてみていきます。
定額減税額
定額減税額について、おさらいをしておきましょう。
定額減税額は、同一生計配偶者と扶養親族の数に応じて金額が決定されます。同一生計配偶者と扶養親族の定義は、次のとおりです。
同一生計配偶者:12月31日の現況で、納税者と生計を一にする配偶者で、年間の合計所得金額が48万円以下の人 扶養親族: 12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人 1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。) または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること 2)納税者と生計を一にしていること 3)年間の合計所得金額が48万円以下であること 4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと または白色申告者の事業専従者でないこと |
具体的な定額減税の額は以下の通りです。
1)日本に居住している本人:30,000円 2)日本に居住している同一生計配偶者または扶養親族:一人につき30,000円 例えば、同一生計配偶者:あり 扶養親族:2名の場合は、120,000円が減税額になります。 30,000円(本人分)+90,000円(同一生計配偶者と扶養親族の合計)=120,000円 |
減税が行われるタイミングは、2024年6月1日以後最初に支払われる給与や賞与に課税される所得税から減税が行われています。6月に支払われる給与や賞与から定額減税額を控除しても、控除しきれない部分の金額については、2024年中に支払われる給与や賞与から順次控除されています。
また、年末調整時に、最終的な所得税額に応じて定額減税が行われ、全額を控除できた場合は所得税における定額減税は終了になります。
全額を控除できたかどうかは、源泉徴収票を見ると判ります。基本的には、源泉徴収票で最終的に源泉所得税が発生していれば全額を控除できたことになり、源泉所得税額が0円の場合は控除しきれなかった可能性があることになります。
定額減税をしききれなかった場合の給付について
住宅ローン控除などの影響で、定額減税しきれないと見込まれる方は、2024年に当初給付が支給されました。一方で、子どもの出生や親を扶養に入れたときなど、扶養親族が増加したときや、給与や賞与から引き切れなかった場合は、2025年に不足額給付を受けることになります。
当初給付と不足額給付については、次のように定義されています。
1)当初給付: 2024年夏以降、個人住民税が課税される市区町村において、2023年の所得状況に基づき、定額減税で引ききれないと見込まれる対象者に概算額を支給 2)不足額給付: 個人住民税が課税される市区町村において、2024年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、追加で支給 |
不足額給付は、2024年分の所得税と定額減税の実績の額が確定する必要があるため、2025年に個人住民税が課税される市区町村から支給されることになっています。
不足額給付の算定については、所得税の控除不足額と個人住民税の控除不足額を足した金額を1万円単位で切り上げて算出した額から、当初給付額を差し引いた額が支給されます。
不足額給付の申請方法について
不足額給付の支給対象者は、市区町村から本人へ確認書が送付される予定です。送付された書類を確認し、必要事項を記入の上、行政に返信して対応してください。
なお、支給の時期は、市区町村ごとに異なります。そのため、詳細については、2025年1月1日に住所がある市区町村の情報をご確認ください。
今回は、定額減税で引き切れなかった場合の給付についてみてきました。不足額給付は、会社ではなく、市区町村が担当します。そのため、市区町村によって必要な手続きが異なる場合があります。従業員から問い合わせがあったときは、本人から1月1日現在居住していた各市区町村に確認してもらうようにしましょう。
鈴与シンワート株式会社が提供する人事・給与・勤怠業務と財務・会計業務ソリューションはこちらからご覧ください。
-
第144回兼業や副業の場合の割増賃金と今後の方向性
-
第143回2025年度税制改正について
-
第142回社会保険の報酬と月額変更
-
第141回定額減税の残額の給付
-
第140回社会保険における年収の壁
-
第139回年収の壁の種類と103万円の壁
-
第138回年収の壁の種類と100万円の壁~103万の壁、130万の壁以外にも「壁」がある~
-
第137回対象者の拡大が見込まれるストレスチェック制度
-
第136回アルバイトの1ヶ月単位変形労働時間制の適用
-
第135回健康保険証の廃止
-
第134回育児介護休業の改正
-
第133回労働時間の適正な管理方法
-
第132回バス運転者の改善基準告示~その3
-
第131回バス運転者の改善基準告示~その2
-
第130回バス運転者の改善基準告示~その1
-
第129回タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示~その2
-
第128回タクシー、ハイヤー運転者の改善基準告示
-
第127回トラック運転者の改善基準告示~その2
-
第126回トラック運転者の改善基準告示~その1
-
第125回運送業における時間外労働の上限規制
-
第124回建設業における時間外労働の上限規制
-
第123回最低賃金の対象となる賃金
-
第122回医業における時間外労働の上限規制
-
第121回年次有給休暇と割増賃金
-
第120回会社の管理職と労基法の管理監督者
-
第119回運送業と建設業の労働時間の上限規制
-
第118回給与のデジタル通貨払い~その2
-
第117回給与のデジタル通貨払い
-
第116回障害者雇用率の引き上げ
-
第115回健康経営について
-
第114回社会保険加入の勤務期間要件の変更
-
第113回勤務時間中の喫煙と休憩時間
-
第112回男女の賃金の差異の情報公表~賃金差異の計算方法
-
第111回男女の賃金の差異の情報公表
-
第110回アルコールチェックの義務化
-
第109回新型コロナウイルス感染症の後遺症の労災認定
-
第108回労働時間の判断基準
-
第107回労働時間と休憩時間
-
第106回夜勤シフトと休日の関係
-
第105回有給休暇の買上げ
-
第104回2022年の法改正項目~社会保険の適用拡大と女性活躍法
-
第103回2022年の法改正項目~育児介護休業法の改正
-
第102回2022年の法改正項目~パワーハラスメントの防止対策
-
第101回休憩時間のルール
-
第100回労働者代表の選任
-
第99回令和3年 育児休業法の改正について~その2
-
第98回令和3年 育児休業法の改正について
-
第97回過労死の労災認定基準
-
第96回テレワーク時の労災~通勤災害
-
第95回テレワーク時の労災~その1
-
第94回70歳までの雇用延長~その2
-
第93回70歳までの雇用延長~その1
-
第92回同一労働同一賃金と最高裁判例
-
第91回増加する兼業・副業~その3 通算労働時間の確認方法
-
第90回増加する兼業・副業~その2 労働時間の通算
-
第89回最低賃金の引上げ
-
第88回コロナ感染と通勤災害
-
第87回コロナ感染と労災認定
-
第86回パワハラ防止法~その8
-
第85回パワハラ防止法~その7
-
第84回パワハラ防止法~その6
-
第83回パワハラ防止法~その5
-
第82回パワハラ防止法~その4
-
第81回パワハラ防止法~その3
-
第80回パワハラ防止法~その2
-
第79回パワハラ防止法~その1
-
第78回労働者派遣法の改正~労働者の待遇の情報提供
-
第77回労働者派遣法の改正~その2
-
第76回労働者派遣法の改正~その1
-
第75回1号特定技能外国人の判断基準~その2
-
第74回1号特定技能外国人の判断基準~その1
-
第73回新しい在留資格
-
第72回有期労働契約の解除
-
第71回働き方改革~新36協定の内容
-
第70回働き方改革~36協定の締結内容の変更
-
第69回働き方改革~同一労働同一賃金
-
第68回働き方改革~産業医の活用と機能強化
-
第67回働き方改革~高度プロフェッショナル制度
-
第66回働き方改革~フレックスタイム制の改正
-
第65回働き方改革~その2
-
第64回働き方改革~その1
-
第63回安全衛生管理体制~その2
-
第62回安全衛生管理体制~その1
-
第61回会社が行う健康診断~その2
-
第60回会社が行う健康診断~その1
-
第59回就業規則のいろはのイ
-
第58回労働契約の申込みみなし制度
-
第57回改正労働者派遣法の2018年問題
-
第56回いよいよ始動する無期転換ルール
-
第55回働き方改革を実現するために(その4)
-
第54回働き方改革を実現するために(その3)
-
第53回働き方改革を実現するために(その2)
-
第52回働き方改革を実現するために(その1)
-
第51回病気療養のための休暇や短時間勤務制度
-
第50回年次有給休暇の取得率の向上と一斉付与
-
第49回労働時間等見直しガイドラインの活用
-
第48回テレワークの導入と労働法の考え方
-
第47回管理職と管理監督者の違い
-
第46回同一労働同一賃金の行方
-
第45回時間外労働、休日労働に関する協定の重要性
-
第44回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その5 子の看護休暇等の改正ポイント~
-
第43回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その4 育児介護休業規程の改正ポイント~
-
第42回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その3 子の看護休暇等の改正ポイント~
-
第41回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その2 介護休業の改正ポイント~
-
第40回育児・介護休業法改正と会社の対応 ~その1 育児休業の改正ポイント~
-
第39回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度~その5 高ストレス者への面接指導の方法と注意点~
-
第38回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度~その4 高ストレス者の選定基準と診断結果の通知~
-
第37回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その3 調査票作成編~
-
第36回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その2実施方法編~
-
第35回本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 その1
-
第34回在宅勤務制度と事業場外労働の規程例
-
第33回通勤災害の対象となるケース
-
第32回ついに成立した改正労働者派遣法~その3
-
第31回ついに成立した改正労働者派遣法~その2
-
第30回ついに成立した改正労働者派遣法~その1
-
第29回いよいよ通知がはじまるマイナンバー
-
第28回日本で働くことができる外国人
-
第27回いよいよ成立が見込まれる労働者派遣法
-
第26回休職中の社会保険料の取扱いと休職規定サンプル
-
第25回慶弔休暇のルールは就業規則等で明確にしておこう
-
第24回来年1月開始~マイナンバー制度 その3
-
第23回来年1月開始~マイナンバー制度 その2
-
第22回来年1月開始~マイナンバー制度 その1
-
第21回パートタイム労働法の改正と社会保険の適用
-
第20回急増する労務トラブルの解決機関にはどのようなものがあるか
-
第19回精神障害と労災認定
-
第18回解雇は最終手段?
-
第17回今の法律でもできる、成果で従業員を評価する仕組み
-
第16回労働組合のない会社必見!!~労働組合の基礎知識~
-
第15回残業代を定額で支払うのは
-
第14回法改正が続く有期雇用労働者との雇用契約
-
第13回どんな業種でも起こる労働災害の申請手続き
-
第12回賞与を支給すると逆効果??
-
第11回インターン生であれば労働者ではないのか
-
第10回会社に有給休暇を買い取ってもらえるようになる?
-
第09回アルバイトが引きおこす「悪ふざけ」への人事的対応
-
第08回大々的に行われる「ブラック企業」対策